Simplestar Game
since 17/01/2009
:::::::::::010�b�@�R���s���[�^�ɂ���:::::::::::
�ǂ����C�V���v���X�^�[�ł��D
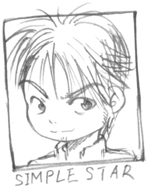
���āI����̓v���O���~���O����ɑ����C�R���s���[�^�ɂ��Ċw��ł݂悤�Ǝv���܂��D
�Ȃ������ɗ��ăR���s���[�^�ɂ��Ċw�Ԃ̂��H
������v���O�����̗����������Ȃ邩���ł��D
����͐F�X����܂����C�݂Ȃ���͂���C++�̊J������"Hello, world!"�������Ă��܂���ˁD
�������C����8�s�̃v���O�����C�݂Ȃ���͈�s��s���̕K�v��������ł���ł��傤���H
�i���P�j�ł��܂��[��D
�����ł��I���S�҂́u�Ȃ��H�v�̋^��������Ȃ���v���O���������ǂݐi�߂Ă��܂��C�����̕��͂����ł�����߂Ă��܂��̂ł��I
�Ⴆ�\�u�|�C���^�������ł��Ȃ��I�v���O�������l�������Ȃ��C�������C�����d���Ŏg�������Ȃ��I�v�Ƃ�������ł��D
���͌��ݗ��n�̑�w�@�Ŋw���Ă�����Ă܂����C�����̓����̊w������������ɂ��܂��D(2009�N�̂���)
���ǂ݂�ȃC���C�������Ďg����悤�ɂȂ��Ă܂����u�|�C���^�͗����ł��邯�ǁC�R���s���[�^�Ƃ̊W�͂悭�킩��Ȃ��D�v�Ƃ����܂��D
���̍l���́C��ɃR���s���[�^�ƃv���O�����̊W���w�ׂv���O�����̗����������Ȃ�C�v���O�������D���ɂȂ�̂ł͂Ȃ���
�Ƃ����P���Ȃ��̂Ȃ̂ł��D
�u���Ⴀ�R���s���[�^�ɂ��ĕ����Ă݂悤���ȁH�v�Ə����ł��v�������͖{���b�X����ǂ�ł����Ɓc���ꂵ���ȁI
����ł́C�܂��̓R���s���[�^�̗��j����@�i�����������Ȃ�܂��c�e�L�X�g�Ƃ��Ă͎��i�ł����C�����Ăˁj
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�y�����āC���������m�Ɍv�Z���ʂ����C����͐̂���l�̊肢�ł����D
�d�q�v�Z�@���o�ꂷ��܂ŁC���ԂƂ���K���g���đ����Z������Z�C�|���Z�⊄��Z������@�B����������Ă��܂����D
�u�����v�����̈�ŁC�����̊��̎��ォ����p������Ă��܂����D�i���j����܂���ˁj
���E�ōŏ��̓d�q�v�Z�@��1942�N�ɃA�C�I���B����w�ō��ꂽ�����ł��D
Atanasoff�@�Ɓ@Berry�@�� Computer�@�Ƃ������ƂŁC�����āuABC�v�ƌĂт܂��D
�uABC�v�͑�Q�����E��풆�C�R���ړI�Ŕ閧���Ɍ������ꂽ���̂ł����D
�����ƃ������i�L�����u�j�������Ă��āC�^��ǂ��g�����d�q��H�Ōv�Z���s���܂����D
1948�N
���o�ꂵ�܂��D�i20���I�̎O�唭���̂����̈�ł��I���Z���ȏ�͓���̌��������ł��ǂ݂܂��傤�j
�^��ǂɂƂ��đ���C�g�����W�X�^���d�q��H�̑f�q�Ƃ��Ċ��܂��D
�Ղ��イ�H�i�����牌���c�j
�������Ȃ��C���S�҂̐��P�ɂ��킩��悤�ɊȒP�ɐ��������
���Ԃ��K���g���ċ@�B�I�ɂ���܂ŏo���Ă������Z���C�d�C�������d�q��H�ɔC���邱�ƂŁC�������Ōv�Z�ł���悤�ɂȂ����D
�����Ɗw�т����l�̂��߂ɁC�킩��₷���T�C�g���Љ�܂��D�i�ȉ��C���̑����܂œǂݔ���ĉ������j
���̃T�C�g�́@�U�@���j�i�T�v�����Ɨ��j�N�\�@�`�L�j ���@�d�C�̗��j�@�Ɠǂ�ł݂ĉ������D
�i�Z�����͂ŁC�d�C�̌ꌹ���猻��Z�p�܂ł܂Ƃ߂Ă��܂��c�d�C�Ɋւ���l�ނ̋O�Ղ��w�ׂ܂��I�j
�܂��C�@�V�@�d�C���p ���@�d�q�v�Z�@�̘_����H�@���@(�P)��{�_����H�@�ƌ��ĉ������D�i�ǂ܂Ȃ��Č��邾���ł��D�j
AND,OR,NOT,NAND,NOR�ƊG������ƁC�g�����W�X�^�C��R�C�_�C�I�[�h�őS�č\������Ă��邱�ƂɋC�t���Ǝv���܂��D
�Ȃ������b�Ƃ��āC���̂R�̓E�G�n�ƌĂ��V���R���̔��[���Ɉ������悤�ɂ��č�邱�Ƃ��o����̂ł��D
����ɂ��C�ǂꂾ��������������邩���W�ϗ��C���^���̘b�ɂȂ�̂ł����C�M�����Ȃ����Ƃ�
���̖����@�B�Z�p�҂����낵�������ʼn������Ă��܂��܂����D�i�R���s���[�^�Z�p�҂��C�����܂ő����i������Ƃ͎v��Ȃ����������ł��j
�@�B�H�C�������ł��ˁc
�X�e�b�p�[�ƌĂ�郌���Y�̉������̂悤�ȑ��u�ŁC��H�v�}���k�����Ĉ������̂ł���
���w�C�͊w�C�U���C�ޗ��C�M�C���̂̃G�L�X�p�[�g�ł���Z�p�҂������C���\�N�Ƃ��̃X�e�b�p�[�����ǂ��Ă��܂����D
�u���_���������ȏ㏬�������܂���v�Ƃ������܂ō�荞��ł��܂��C�W�ϗ��͌��E���}���������ł��D�i���낻��V�Z�p���o�邩���I�H�j
���Ƃ́C��H�̐v�҂��ǂꂾ���f���炵���v�}��`�����ɂ������Ă��܂��D
�ǂ��`���Ƒf���炵���Ȃ�̂��C�܂������Ă��܂��C����܂������ȕ�����ɂ߂��G�L�X�p�[�g�ɂ������Ȃ����̂��Ɨ\�z���Ă܂��D
1000�l�̗D�G�ȋZ�p�҂�3�N�ԍl�����C���y�[�W3�����̐v�}�Ƃ�����ȃC���[�W������Ă��܂����C���ۂǂ��Ȃ�ł��傤�H
�ŋ߂̓}���`�R�A�ŁC���\�����ڎw���Ă���Ƃ������Ă܂����C���������ėD�G�Ȉ�l����|���Ă����肵�āH
�i��011�b�ŃR�A�ɂ��Ċw�т܂��j
�Ƃ���ŁC�R���s���[�^�͑����Z�����o���Ȃ���ł���D
���I�����Ȃ́H

�����Z�����H�@�ł��p�\�R���͍D���ȉ��y�̃_�E�����[�h��
�F�XWeb�T�C�g�̉{���C����ɃQ�[���Ƃ��ŗV�ׂ邶���D
�܂������C���O�́c���ꂶ��V�т̓����Ȃ����I
���͂܂��p�\�R���̘b�����Ă��܂���D�����܂ŁC�܂��d�q�v�Z�@�̘b�������Ă��Ȃ��̂ł��D
���m�ɂ́C��{�_����H��g�ݍ��킹�����Z��H�ł̑����Z�����R���s���[�^�͍s���Ȃ����Ƃ������܂����D
(
�d�C�̗��j�C���X�g�����Љ�������ł���)
�������C�ʔ������Ƃɂ��̉��Z��H��g�ݍ��킹��Ό��Z�C��Z�C���Z��H���o����
�����Z�C�|���Z�C����Z���ł���悤�ɂȂ�܂��D�i�l�Ԃ͖{���ɓ����ǂ��ł��ˁj
���̂ق��ɁC�f�[�^���i�[����@�\�����C�ǂݏo���Ə������݂��s����悤�ɂ��܂����D
����ɂ��C�w�肵���ꏊ���琔����ǂ݂����C���Z���s���C���ʂ��w�肵���ꏊ�֏������ނ��Ƃ��o����悤�ɂȂ�܂��D
���ꂪ�C�R���s���[�^�̖{���ł��D
�����ŁC�p�\�R���ɂ��čl���Ă݂܂��傤
�l�Ԃ��L�[�{�[�h�Ōv�Z���߂���͂��C�R���s���[�^�͖��ߒʂ�v�Z���C�v�Z���ʂ����j�^��X�s�[�J�[�ɏo�͂���D
�o�͂̎d���ɂ��F�X�H�v�����邯��ǁC�u���́��v�Z���o�́v�C����̌J��Ԃ����s���V�X�e�����p�\�R���Ȃ�ł��D
�H�ł����C���܂Ōv�Z���߂�^���悤�Ȃ�āC�l���ăp�\�R���ɐG�������ƂȂ����ǁD
�����v�킹�Ȃ��悤�ɁC�G�����āC�����I�ɑ���ł���V�X�e���C���ꂪGUI (�O���t�B�J���E���[�U�E�C���^�t�F�[�X)�Ȃ̂��D
�l�ƃ}�V�����Ȃ��C�q���[�}���E�}�V���E�C���^�t�F�[�X�Ƃ������܂��D
OS�i�I�y���[�e�B���O�E�V�X�e���j�Ƃ��Ă�Ă���C�\�t�g�E�F�A�ł��D
�C���^�t�F�[�X�C�\�t�g�E�F�A�c������ăv���O�����Ȃ́H
���̒ʂ�I�l�Ԃ̒����ƁC�R���s���[�^�̘_���̊ԂŃN�b�V�����̂悤�ɓ����v���O�����D
�����ʂ��āC��X�͍��u���v�āC�����āu�m���v�ɕς��悤�Ƃ��Ă���̂ł��D
�ł͎��ɃR���s���[�^�ɗ^���閽�߂ɂ��ďڂ����w��ł݂܂��傤�D
�����[�I�H�����́C�������܂����D�܂����x�Łc
�������c�ł́C�܂Ƃ߂܂��D
- �R���s���[�^�͑����Z�����o���Ȃ� -
���̂��Ƃ�������Ɨ������Ď��ɐi�݂܂��傤�D
2009/08/24 ���L�D
2009/08/28 �����D
2009/09/27 �C���D